中学受験において、植物分野は重要な出題範囲の一つです。しかし、多くの受験生が、植物の覚え方に苦戦しています。この記事では、中学受験における植...


皆さんこんにちは。
SS-1理科講師の村橋です。
サピックス5年生の皆さんへ、今週の理科の攻略ポイントをお届けします!
「動物の分類」の攻略ポイントは、表で水準をそろえて整理することです。
➀昆虫
➁昆虫の行動
➂無セキツイ動物
昆虫のからだのつくりで整理しておきたいものは次の3つです。
・触角の形
昆虫ごとに答えられるように確認しましょう。
・あしの形・口の形とえさ
形は理由とともに覚えましょう。
また、知らない昆虫は調べて写真で出題されても選べるようにしましょう。
(例)タガメ:「えものをとらえる」ために、あしの形は「するどくなっている」
(例)セミ:「木の汁を吸う」ために、口の形は「針のようになっている」
・気門と気管
気門は、腹の位置に空いている穴のことです。
そのため、昆虫は頭を水にしずめても窒息してしまうことはありません。
昆虫の冬ごしは次のものから覚えていきましょう。

幼虫で冬ごしをするカブトムシとセミは土の中で、ヤゴ(トンボの幼虫)は水の中で寒さをしのぎます。
成虫で冬ごしをするアリやハチは巣の中で冬眠をするようにして冬をこします。
また、昆虫の鳴き声は、秋の虫とセミを押さえましょう。
併せて、鳴くのはメスへのアピールのためなので、オスであることも確認しておきます。
鳴き声は、YouTubeなどで実際に聞くこともお勧めです。
無セキツイ動物の分類は表で整理しましょう。

節足動物は足の本数で分けましょう。
昆虫類は6本、クモ類は8本、甲殻類は10本(ダンゴムシは14本)、多足類はたくさんです。
また、覚えておきたいものは、クモ類のサソリ、甲殻類のミジンコです。
軟体動物で覚えておきたいものは、貝(アサリ)です。
その他の動物は、軟体動物とのひっかけで出題されます。覚えておきたいものは、ミミズとクラゲです。
動物の分類は、表で水準をそろえて整理することが大切です。
理科の成績を何とかしたいとお悩みでしたら、最寄のSS-1の教室にご相談ください。無料の学習カウンセリングを行わせていただき、お子様に応じたベストアドバイスを差し上げます。
↓
学習カウンセリングお申込みはコチラ

この相談に答えた講師
村橋 寛人(Murahashi Hiroto)
中学受験専門のプロ個別指導教室SS-1(エスエスワン)理科教務主任。関東にあるSS-1横浜教室を中心に指導しており、中学受験を目指すお子さんを難関中学に送り出しています。生徒さんが問題文のどこを見て、何を感じ、どう判断したのかを考え抜き、授業では「自分で気付ける」ような問いかけを徹底する講師です。生徒さんからも「柔らかく何でも話しやすい」という声が多く集まっています。

テスト前は算数や理科、社会の対策に追われ、国語の勉強が後回しになったり、何をすればよいか分からず諦めてしまったりする声をよく聞きます。 今回...

中学受験国語でよく出題される「比喩」の問題は、苦手とする小学生が少なくありません。本稿では、その「比喩」に注目し、どのように読み解いていくか...

模試や過去問を見返すと、記述だけが空欄のまま残る。時間は使っているのに、いざ書く段になると手が止まる。 こうした現象は、最近の生徒によく起こ...

今週の攻略ポイント 皆さんこんにちは。SS-1理科講師の村橋です。 サピックス5年生の皆さんへ、今週の理科の攻略ポイントをお届けします! 「...

随筆文は「体験」と「感想」でできている 説明文は事実を伝える文章、論説文は筆者の主張を述べる文章、物語文はフィクションの世界を通じて感情を表...
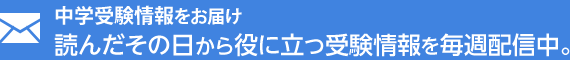
SS-1の無料メルマガ『Challenge Eyes』では、中学受験専門の個別指導ノウハウが詰まった塾の成績アップ情報をお届けしています。