夏休みは「中学受験の天王山」 小6の夏休みは「中学受験の天王山」と呼ばれる重要な時期です。日能研6年生の夏期講習テキストは、4科目が一冊にな...


中学受験を間近に控えたお子さまを持つ保護者の方にとって、「子どもが本気で勉強に取り組むのは一体いつなのか?」という疑問は大きいのではないでしょうか。
しかし、「本気になってほしい」と思っても、なかなかそうならない子どもが多いのも事実。では、子どもたちが"やる気スイッチ"を入れるタイミングとは、どのようなものなのでしょうか?
この記事では、子どものやる気が起こる時期や流れを解説したうえで、「大人が考える本気」と「子どもが示す本気」がなぜ異なるのか、そして本気を引き出すためのポイントをお伝えします。
最後には、親子の受験をサポートしてきた個別指導塾SS-1のご紹介もありますので、ぜひ最後までご覧ください。

子どものやる気は、大人が思うような「早い段階での完全燃焼」ではなく、周囲の雰囲気や友だちの動向を見ながら少しずつ高まっていきます。以下に、一般的によく見られるタイミングをまとめました。
過去問が始まり現実的な点数が見えてきて「大人が本気で焦り始める」のがおおよそ6年9月ごろです。その親の緊張感を敏感にキャッチし、不安になるのがこのタイプ。
大人より1ヶ月ほど遅れた10月ごろに不安で眠れなくなったり、突然泣き出してしまったりします。
基本的にこのタイプのお子さんは、前から勉強しているはずですので、安心させてあげることを優先するとよいでしょう。
子どもは成長するにつれて、親よりも友だちを優先するようになります。
親に認められるよりも、友だちに認められたいという気持ちの方が強くなっていくのです。そんな、少し大人びた生徒が本気を見せるのが11月ごろです。
周囲の友だちが不安になっているのを見て、自分もこのままではいけないのではないかと焦り始めるのです。
言われたことはやるが自ら動き出さないタイプの子どもが自立して勉強し始めるのがこの時期です。本気で勉強し始めた子どもは会話も別人になります。
「この前解いた過去問で8割取れたんだよね」「天体が苦手単元だから勉強しないといけないんだ」このような会話がちらほらと子どもたちの中でされるようになってきます。
これらの言葉を聞いて、言われた通りにやっているだけでは受からないかもしれないと気づくのが12月ごろなのです。
1月のお試し受験(関東)が始まり初めての不合格を経験したときに焦るタイプ。ここで少し難しめの学校に合格してしまうとより安心してしまい最後までまったく焦らなくなってしまう、ということもあります。
このタイプに当てはまる生徒は1月のお試し受験で合格と不合格の両方を取りに行って、あえて危機感を煽るのも手です。
このように、「もっと早く本気を出してほしい」と思っても、子どもはそれぞれの性格や環境によって一気にエンジンがかかるタイミングが異なります。
本気になるのは「6年10月!?」と思われるかもしれませんが、実際、このくらいの時期にならないと大人の考える本気は見えてこないのが実情です。

子どもたちのやる気が起こる時期はバラバラなうえに、私たち大人が想像している「本気」とはそもそも基準が違います。大人目線では、「毎日自主的に数時間の勉強をこなして、自ら課題を解決する」ような状態を"本気"だととらえがちです。
しかし、個別塾の中で、はじめから大人の考える本気を備えていたお子さんは本当に一握りです。
私が見てきた生徒さんの例だと「音楽をやらせたいご家庭で、勉強に逃げていた女の子」「6人兄弟の長男で、両親が勉強はおろか送り迎えもできない状態にあり、自立して勉強せざるを得なかった男の子」「周りに塾がなく、東京の中学校に行くために自分で参考書を読んで勉強するしかなかった女の子」など、どのお子さんも「一人で勉強するしかなかった環境」に置かれていました。
そして「本当の意味で勉強を強制されていない環境」でもありました。このように自立をして勉強をするのは「環境」そのものが特殊でないと難しいのです。
だからこそ「昨日より少し速く計算ができるようになった」「今日はいつもより早く机に向かえた」など、小さな変化からやる気を引き出してあげる必要があるのです。大人が待ち望む大きな成果は、こうした積み重ねの"最終段階"として、あるとき表面化してくるのです。

子どものやる気を引き出すためには、大人の理想を押し付けるのではなく、子ども自身が「もう少し頑張ってみよう」と思えるように、小さな本気に「価値づけ」をしてあげないといけません。
こういった"ちょっとした進歩"を見つけて褒めてあげることで、子どものモチベーションは着実に上がります。
子どもは周囲に左右されやすい一方、追い詰められすぎると萎縮してしまうことも少なくありません。だからこそ「少し危機感を持たせつつ、追い詰めすぎない」というバランスが大切になります。
子どもにとっては、大人が少し焦っている様子が伝わるだけでも「そろそろやらなきゃ」という気持ちが芽生えるもの。一方で、毎日のように叱られ続けてしまうと、「自分はダメなんだ」と思い込んでしまい、やる気どころか自信まで失ってしまうケースもあります。
一方で、まったく叱らないのがいいわけでもありません。本当に守るべき約束(例:就寝時間、宿題の提出など)は毅然と守らせることが必要です。
子どもがルールを破ったときにはしっかりと注意し、「なぜそれがいけないか」「次はどうすればいいか」を具体的に伝えましょう。「叱るときには"感情的に怒る"のではなく、"ルールに反した行動を正す"」というスタンスを貫くことが大切です。

ここまでお伝えしてきたように、子どものやる気が高まるタイミングやきっかけは、性格や環境によって本当にさまざまです。そのため、保護者が一人で悩んでいると、どうしても「本当にこのままでいいの?」と不安になり、子どもにプレッシャーをかけすぎてしまうこともあるでしょう。
もし「なかなかやる気を引き出せない」「何をどう勉強させたらいいかわからない」という不安があるなら、第三者の力を借りるのもひとつの方法です。
個別指導塾 SS-1 では、生徒の自立と成長を応援するオンライン自習サポートサービス「モチサポ」を提供しています。小学生の自立の難しさを一番よく理解しているSS-1の講師陣だからこそできる、本気で考えたサービスです。
「モチサポ」は、自宅でも教室でも受講できるオンライン自習サポートサービスです。正面と手元の2画面を活用し、講師が生徒の自習の様子を細かく観察します。
さらに、適切な声掛けと学習方法のアドバイスを行うことで、集中力の持続を助け、自習の量と質を高めます。
小学生が自習に意欲的に取り組むためには、「感情報酬を与えること」と「立ち止まる時間をなくすこと」が重要です。
通常、子どもが自習で工夫したことや努力したことは誰にも気づかれにくいものですが、モチサポではそれをしっかり見つけ、全力で褒めることでモチベーションを高めます。
また、学習の進め方や解き方に迷って手が止まると、やる気が削がれ、ダラダラとした勉強になりがちです。モチサポでは、その兆候をキャッチして声掛けを行うことで、立ち止まる時間を最小限にし、モチベーションを維持できるようサポートします。
中学受験生の多くは、膨大な課題に追われ、学習の負担を感じています。
モチサポのようなサポートを活用することで、学習を効率よく進め、適切に息抜きする時間を確保できるようになります。その結果、学びに対する前向きな姿勢を保つことが可能になります。
実際にモチサポを受講した生徒からは、「ふだんの自習より圧倒的に集中できた!」「先生に褒めてもらえてやる気が出た!」といった声が寄せられています。小学生のやる気を引き出すために、モチサポは非常に効果的なサポートと言えるでしょう。

中学受験は、子どもにとって大きなチャレンジですが、保護者の皆さんにとっても長期にわたるサポートが必要な大きな試練です。だからこそ「なかなか本気にならない」「早くやる気を起こしてほしい」と焦るお気持ちはよくわかります。
しかし、子どもの本気スイッチには"時差"があります。周囲の状況や自分の中の「まずい」という感覚が少しずつ育っていき、最終的に大きな変化として表面化するのです。そこを理解しながら、親子で「やってみよう」「できるかも」と思える瞬間を少しずつ増やしていきませんか?
「もっと早くエンジンをかけてほしい」「どうサポートしたらいいか分からない」といったお悩みは、ぜひSS-1へご相談ください。一人ひとりの状況を丁寧にヒアリングし、やる気の土台づくりからしっかりサポートいたします。
一緒に、子どもの可能性を広げる中学受験を実現していきましょう。

この相談に答えた講師
田畠 靖大(Tabata Yasuhiro)
中学受験専門のプロ個別指導教室SS-1(エスエスワン)国語科講師。関東にあるSS-1白金台教室、渋谷教室、お茶の水教室や、オンライン教室でも全国の生徒さんを指導しており、毎年難関中学に送り出しています。担当教科は国語・算数。論理性を重視しながらも、ソフトな語り口でお子様の課題解決に取り組みます。テストでの得点向上のみならず、科目の根本理解、体系理解を実現、得意科目に仕上げていきます。

テスト前は算数や理科、社会の対策に追われ、国語の勉強が後回しになったり、何をすればよいか分からず諦めてしまったりする声をよく聞きます。 今回...

中学受験国語でよく出題される「比喩」の問題は、苦手とする小学生が少なくありません。本稿では、その「比喩」に注目し、どのように読み解いていくか...

模試や過去問を見返すと、記述だけが空欄のまま残る。時間は使っているのに、いざ書く段になると手が止まる。 こうした現象は、最近の生徒によく起こ...

1.読書は何年生から始めるべき? 「読書好きの子は必ず国語が得意」というわけではありませんが、「読書習慣があると"国語の成績を上げやすい"」...

随筆文は「体験」と「感想」でできている 説明文は事実を伝える文章、論説文は筆者の主張を述べる文章、物語文はフィクションの世界を通じて感情を表...
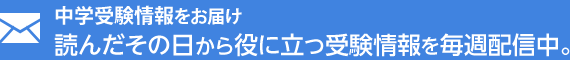
SS-1の無料メルマガ『Challenge Eyes』では、中学受験専門の個別指導ノウハウが詰まった塾の成績アップ情報をお届けしています。