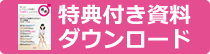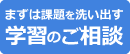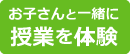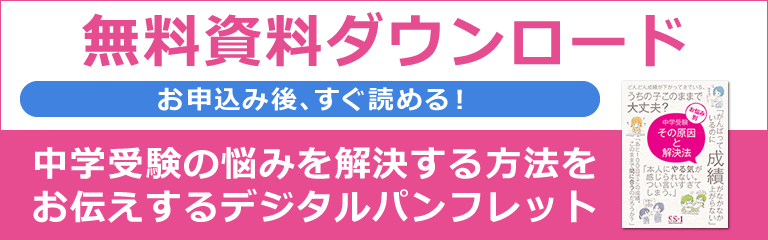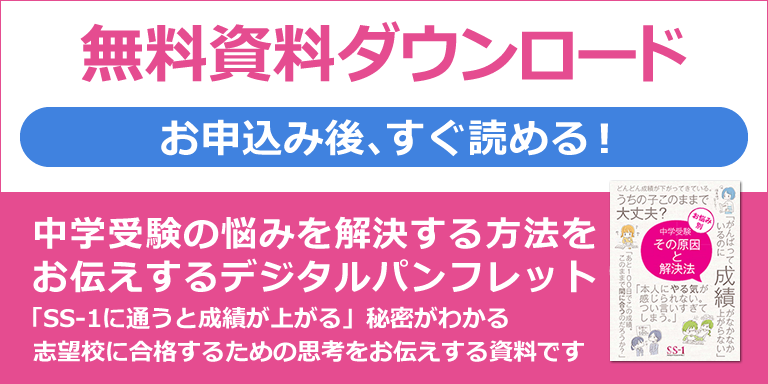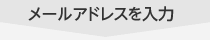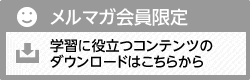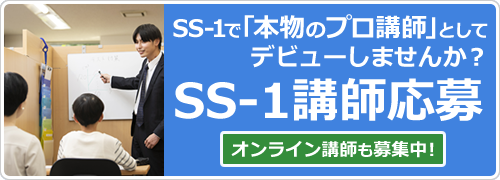塾別 成績の上げ方[四谷大塚]
四谷大塚の合格の決め方冊子を手に入れる
長文を読むのに時間がかかってしまいます
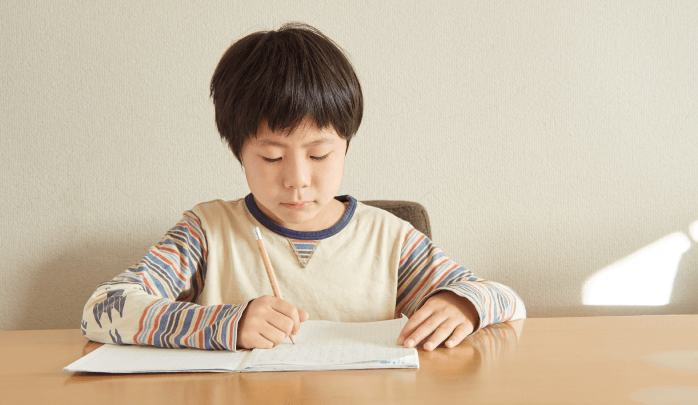

四谷大塚の豊洲校舎に通う小学5年生です。
長文を読むのに時間がかかってしまい、テストの時間が足りなくなってしまうそうです。
読むスピードをアップするにはどのようにしたらいいのでしょうか。

この度はご相談ありがとうございます。四谷大塚にお通いなのですね。
5年生の秋になると各種テストで文章の難易度が上がり、分量も増してきます。
今までは苦手ながらもついていけた読解で、つまずくお子様も多いようです。
お悩みは「長さ」による時間不足とお見受けしますが、使用語句や物語・論理構造の難しさのゆえに読解に時間がかかることもあります。
実は大抵の場合、両者は二つながら組み合わさっています。
「読解が遅くてテストで時間がなくなってしまう」のは、おおよそ次のようなプロセスで生じるといってよいでしょう。
たとえば時空間が前後交錯する長い物語文、あるいはやたら見慣れない語句が並んでいる論説文などは、読んでいるうちに意味がわからなくなり、そのうちに目だけで文字を追うようになってしまいます。
最後まで文字を追いきっても、頭に入っていないので、設問を解こうと思うとまた読み直して解答ヒントやキーを探しますが、見つからないので焦ってますます探せなくなります。
対策としては、
- 頭の中で長い文を適度にブロック分けしながら読むこと
- ものによっては設問を行いながら読んでいくこと
- 短くてもさまざまなパターンの文章を数多く読むこと
などが考えられます。
1.頭の中で長い文を適度にブロック分けしながら読むことについて
物語なら場面の区切りや会話文と描写部分(その中でも説明・情景描写部分と心情描写部分)の境目など、説明文や論説文では「しかし」「ところが」「たとえば」といった接続詞を合図としてブロックごとに区切って読みます。
つまり、「文章構造をおさえて読む。」ということです。
ブロック分けを意図して読むことの最大のメリットは、設問に取りかかったときにどこに何が書いてあるか、だいたい見当がつくことです。
解答するために必要な情報やキーワードとなる語句がどこにあるのかわからずにあちこち探し回る時間も格段に短くなります。
ご家庭では、時や場所の変わり目、会話の始まる前後を狙い、「今どこになったの?」「ここまでで何が起きたの?」といった言葉で作為的に思考整理を促します。
慣れてきたら、「話題の区切れ目に目印をつける」ように導いてあげるとよいでしょう。
2.ものによっては設問を行いながら読んでいくことについて
最近では大人でも時間内に解くのは不可能なのではと感じる長さで課題文が出されることも多くなりました。
理想は課題文を全て読んでから設問に臨むことですが、ものによってはその場であたりをつけた方が効率がよい場合もあります。
ただ、そもそも小学生のお子様には非常に高難易度であることを抑えておいてください。
解答の根拠ぼう線部の前後であれば、特にこのアプローチは有効ですが、そうでない場合は逆に時間がかかることもあります。
1に挙げたように、具体例の先に「まとめ」が書かれるという文章構造など、その構造を理解しながら読むことや、文章を理解しているか確かめながら読むということが自ずと意識に外れていきますので、そこは注意です。
傍線や空欄が出てきたら、少なくとも何を聞かれるのかはその場で掴みます。
前後の段落あたりで答えられる問題は、その場で解いていかないと間に合わないものもあるからです。
ただし、このような長文はたいてい物語文で出題され、設問に正確に答えるための条件は、長い文であればあるほど、傍線とは全然別の箇所(たとえば後の方に書いてある回想シーンの中で)に出てきたりしますから、この解き方には、常に全体に視野を広げて柔軟に対応する心の準備と慎重さが要求されます。
3.短くてもさまざまなパターンの文章を数多く読むことについて
難解な長文を素早く処理していく馬力は、読みながら「予測がつく」という要素が作り出しています。
テストではほとんど初見の問題なのですから、「予測なんかつかない」と思われるかもしれません。
しかし、文章は違っても、人はすでに読んだことのある分野の話題には、初見でもすんなり入っていけるものです。
論理構造が比較的明確な説明文や論説文はとくにパターンがあります。
異文化との接触、環境問題、自然と人間の関係などはとりわけ代表的なジャンルです。
一見違うように見える物語文も、複雑化する家族関係、友情、思春期の心の成長など、大きく分けると似た構造になっています。
多種多様な分野の文章を読んできて、経験値の高いお子さんは、その蓄積を生かして多少難解な文章でも理解できるということです。
予習シリーズにしても実力完成問題集にしても、10~15分あれば読みきれる多様な分野の文章が数多く用意されていますから、漢字練習のように毎日一つでも読解(音読)に勤しみましょう。
それはもちろん、表現や語句の知識を蓄える訓練にもなります。
4.音読練習について
それでも時間内に解けないという場合にご家庭で行っていただきたいのが
「音読練習」です。
音読は「理解できる最低のスピード」です。
このスピードが早くなれば、理解できるスピードも早くなっていきます。
しかし、音読を嫌がるお子様は少なくはありません。
そのため、音読練習の取り組み方法には工夫を凝らすと良いでしょう。
例えば、「交互読み」といって、親御様と交互に読み、どれくらいのスピードで読めると良いのかをお子様に耳で覚えてもらうという方法が有効的です。
また、音読のスピードの目安は、1分間に400文字程度と言われていますので、タイマーで測ってみるなど様々な試行錯誤をしつつ音読練習をお子様が嫌がらないよう進めて頂ければと思います。
以上、文章読解の処理能力を高め、内容把握に精度と速度を確保する訓練の仕方と、音読練習にてスピードをつけてもらうことをご紹介しました。
ご家庭のみでは対策が困難な場合は、SS-1の教室にご相談ください。
より詳しい分析とアドバイスで、解決へのお手伝いをさせていただきます。
↓
お申込みはこちら

この相談に答えた講師
中学受験 個別指導のSS-1
中学受験 個別指導のSS-1 編集部です。本コーナーは中学受験を目指すご家庭のお母さん、お父さんから実際に成績や学習に関するお悩みについてご相談いただいた経験をもとに、中学受験専門のプロ講師による学習アドバイスを発信している中学受験ブログです。皆さまの中学受験のお役に立ちましたら幸いです。
SS-1とは…「今、やっておくべき学習」だけをプロ講師が効率良く教え、最短で四谷大塚の成績を上げることで、中学受験を成功に導く完全1対1の個別指導教室です。
四谷大塚にお通いで、もし成績がなかなか上がらないとお悩みであれば、今すぐに成績が上がる学習に切り替える必要があります。SS-1では、初回の体験授業で「お子さんが成績を上げるための学習方法」をご提示できます。お子さんの成績でお悩みの方は、まずはSS-1の授業をご体験ください。
お子さんだけの成績の上げ方をお渡しします。
SS-1の2つの選べる無料体験を今すぐお試しください。

- お母さんだけで、相談できる学習カウンセリングは
こちらから - お子さんの今必要な課題が分かる学習カウンセリング付き
無料体験授業は
こちらから
中学受験の学年別対策
- 良い学習習慣を身に付けよう中学受験を目指す
4年生の皆さんへ - 基礎と苦手克服が成功のカギ中学受験を目指す
5年生の皆さんへ
中学受験に役立つ受験情報をLINE公式アカウント・メールマガジンで配信中!
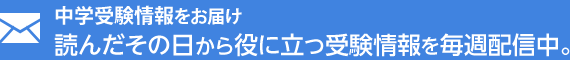
塾のクラスを上げるには?
成績を上げる方法とは?
SS-1のLINE公式アカウントまたは無料メールマガジン『Challenge Eyes』にご登録いただくと、中学受験専門の個別指導ノウハウが詰まった塾の成績アップに役立つ情報や限定セミナーのご案内をお届けします。
迷惑メール対策としてフィルタリング設定をご利用の場合は、ss-1.netドメインからのメールを受信できるよう設定をお願いいたします。
【四谷大塚】テストの成績の事で悩んでいる方にオススメの記事
- 組分けテストで国語の点数が大幅に下がってしまいました
- 四谷大塚・早稲アカ5年生 7月組分けテスト 算数の攻略ポイント
- サピックス5年生 6月マンスリーテスト算数 2つの攻略ポイント
- 難関中を目指していますが国語の成績が足を引っ張り悩んでいます。
- 浜学園へ転塾しましたが期待した結果が得られず悩んでいます