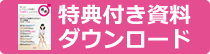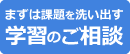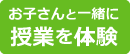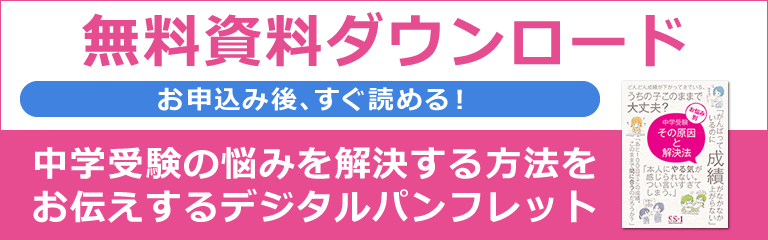上手な春の過ごし方とは?

いよいよ4月から新学年。
学校でも入学式、始業式など、春ならではの行事が行われ、その後、本格的な新学年の生活がスタートします。
ところで、公立・私立の違いや地域による違いはありますが、参観や修学旅行などの代休など、学校の年間行事予定表を眺めてみると、けっこう「お休み」ってあるものです。
私立の学校では、創立記念日による休日や、単なる「家庭学習日」というのも存在するようです。
また4月29日の「昭和の日」や5月初旬の3連休など、もともと休みと決まっている日もありますね。
お子さんたちは、やはり学校が休みであれば「遊びたい!」のでしょうが、「休みだけど、やることがないからダラダラ過ごしてしまった」といった使い方はもったいない!
今号では、こういった学校のお休みを上手に活用する方法を考えていきましょう。
1.休日を把握する
まずは、お子さんの通っている学校の休日はいつなのか、しっかり把握しましょう。
祝日などはもちろん、お通いの学校特有の休日や、懇談や地域行事による早帰りの日などもチェックします。
【ある私立小学校の行事予定】
たとえばある小学校では、始業式が4月10日、学校に行く日は4月は月の半分くらいしかありません。始業式は午前中だけの通学です。
また、5月はGWによる休日のほかに創立記念日による休日があり、6年生には修学旅行の代休があります。
一方7月になると、臨海学校、そしてその準備としての水泳練習。
暑い季節とも相まって、子供たちの体力を奪うイベントが目白押し。
そしてバタバタしているうちに、すぐに夏休み。
特に6年生は、夏期講習が始まると、ほぼ一日中塾に拘束されます。
家庭学習の時間は極端に取りづらくなってしまいます。
ぜひ春のうちに、休日を上手に使う練習をしておきましょう。
∽∽∽∽∽∽∽
☆ 春を上手に過ごすポイント☆
「休日の過ごし方を春の間に練習しておく。」
∽∽∽∽∽∽∽
2.休日の使い方を考える
明日、学校がお休みだということに、お子さんが今日気付いたとしましょう。
せっかくの休みなのだから、何か学習に活かしたいと思っていても、
======
前日:あ、明日は学校が休みだ。
当日朝:時間はあるぞ。何しようかな。
当日夜:今日はダラダラしちゃったな。
======
と、結局あまりたいしたことをせずに1日を終えてしまったり、あるいは、
======
母:明日は学校が休みね。塾の宿題の見直しでもしたら?
子:え~っ!もうやっちゃったからいいよ。
母:何言ってんの!ちゃんとやるのよ!
======
と険悪なムード・・・。
すべて、前もって計画がないからいけないのですね。
さて、こうした休日を有効に使う方法は・・・簡単です!
======
Aあらかじめ休日を把握する。
Bすることを決め、お子さんに伝える。
C実行する。
======
これだけです。簡単でしょう?
大切なことは、AとBをきちんとしておくことです。
Aは、学校の年間行事予定表(なければ月間のものなどクラスで配布されているものを利用しましょう)で把握します。
お子さんが気付くよりも早く、友達と約束してしまう前に、お母様から持ちかけるのです。
「○月○日は学校が休みみたいよ。朝のうちに公開テストの過去問演習をやったらどうかと思うんだけど、どう?」
ここで大切なことは
======
1. 「午前中」「お昼の間」「○時~○時」というように、行う時間を限定する。あとは自由。
2. 普段の塾の宿題などとは別のメニューを用意する。
3. 「○○をすればいいと思うんだけど、どう?」と、お子さんの意見も聞く
======
ということです。
お母様、お父様が物足りなくても、予定した時間がきたら必ず終了する、という決まりを守るようにしましょう。
そうすれば、次の機会にもお子さんは嫌がらずにこのイベントに乗ってきてくれるでしょう。
中学受験に役立つ受験情報をLINE公式アカウント・メールマガジンで配信中!
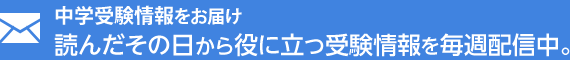
塾のクラスを上げるには?
成績を上げる方法とは?
SS-1のLINE公式アカウントまたは無料メールマガジン『Challenge Eyes』にご登録いただくと、中学受験専門の個別指導ノウハウが詰まった塾の成績アップに役立つ情報や限定セミナーのご案内をお届けします。
迷惑メール対策としてフィルタリング設定をご利用の場合は、ss-1.netドメインからのメールを受信できるよう設定をお願いいたします。